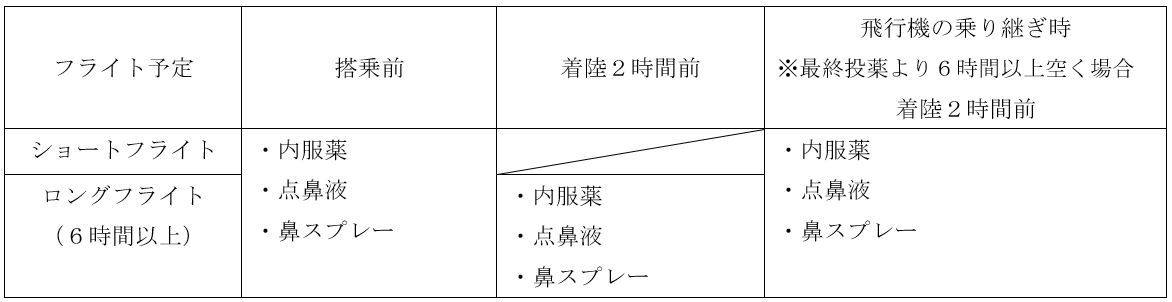|
喉の奥・鼻・耳・目は細い通り道があり繋がっていて鼻→耳に繋がる道を耳管(じかん)といいます。この耳管は中耳(鼓膜の奥の空洞部分)に繋がっていて、空気を中耳に通して中耳内の圧力と外部の気圧を同じにする役割をしています。
この耳管の機能が上手く働かないと中耳内と外部に気圧差が生じて耳痛が起こります。 気圧差が解消されないと航空性中耳炎になることがあります。 |
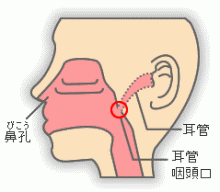
|
 BXI Builingual System started translating.
BXI Builingual System started translating.Language
 BXI Builingual System started translating.
BXI Builingual System started translating.|
喉の奥・鼻・耳・目は細い通り道があり繋がっていて鼻→耳に繋がる道を耳管(じかん)といいます。この耳管は中耳(鼓膜の奥の空洞部分)に繋がっていて、空気を中耳に通して中耳内の圧力と外部の気圧を同じにする役割をしています。
この耳管の機能が上手く働かないと中耳内と外部に気圧差が生じて耳痛が起こります。 気圧差が解消されないと航空性中耳炎になることがあります。 |
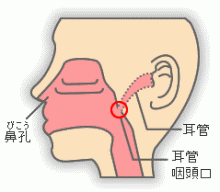
|